慶事・弔事のマナー:香典袋のルール

香典袋には、宗教や宗派に応じて形式が異なることを知っていますか?
はずかしながら、私は香典袋とは1種類だと思っていました。
形式が間違っている香典袋を渡すのは失礼になるので、
通夜やお葬式に参加する際には、事前に確認しておくことをお勧めします!
弔事の表書きも宗教や宗派によって異なる!
香典袋が宗教や宗派によって異なることを紹介しましたが、
実は、弔事の表書きも同じようにバリエーションが様々です。
具体的には、
|
仏式で49日の法要まで→『御霊前』 仏式で49日の法要以降→『御仏前』 法要の時には →『御香料』 神式では →『御榊料』、『玉串料』 キリスト教式 →『御花料』 |
となっています。
『こんなにたくさん種類があると、使い分けられないよ!!』
とあなたは思うかもしれません。
少なくとも、私は思いました。
しかし、安心してください。
なんとどんな時に使ってもOKな表書きがあるのです。
それが、『御供料』です。
迷ったときは、『御供料』と書くと覚えて多くと便利ですよ!
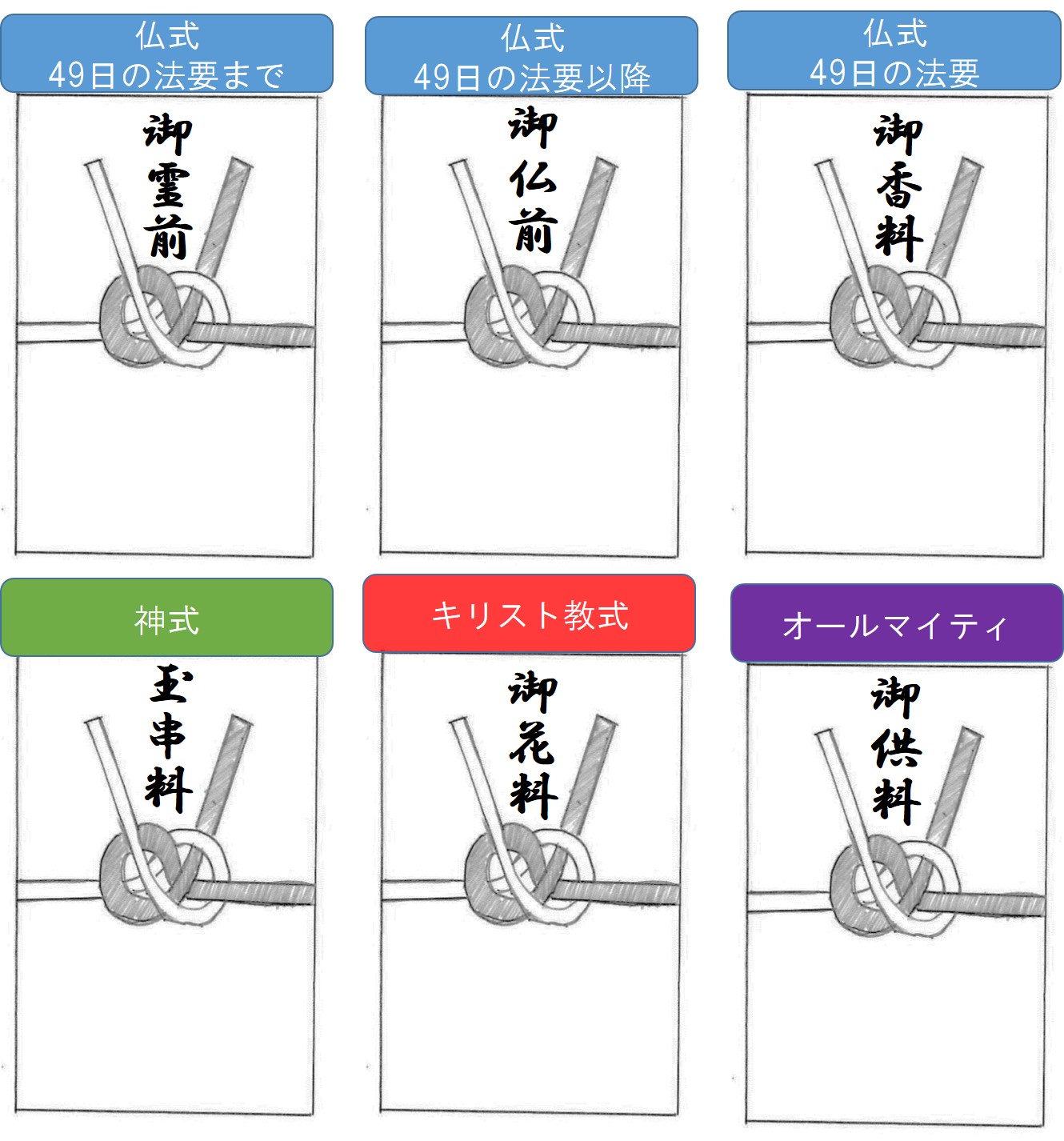


急なお通夜やお葬式では、
香典袋が手元になくコンビニやスーパーに慌てて買いに走ることも
あるかもしれません。(私だけかもしれませんが・・・)
でも、だからといって、香典袋を裸のままで持っていくことは
マナーが出来ていないと見なされます。
かならず、『ふくさ』に包むようにしましょう
「ふくさ」の包み方は2種類ある!
「そうか!香典袋は「ふくさ」に包めばいいんだ!気を付けよう!」
で早合点してはいけません。
「ふくさ」には『慶事』と『弔事』の2種類の包み方があるのです。
簡単に言うと
慶事の場合は、開きが右にくるように
弔事の場合は、開きが左にくるように包むのがマナーです。

では実際の具体的な包み方を見てみましょう!
《慶事(ご祝儀袋などを包む)ver》

《弔事(香典袋などを包む)ver》

さらに注意したいのが、「ふくさ」には慶事・弔事で
色を使い分けなければいけないというルールがあるのですが、
『紫』に関しては、どちらでもOKなオールマイティな色なので、
紫色のふくさを1つ用意しておくとよいでしょう!
「ふくさ」には挟みふくさと呼ばれる、便利なモノもあるので、
そもそも包み方を覚えるのが面倒な方は、「紫色の挟みふくさ」を
用意しておけば良いと思います。
香典袋はふくさを台にして
「ふくさの包み方、バッチリ!」
「ふくさの色、バッチリ!」
だとしても、渡し方がなっていないと、やっぱり
「マナーが出来ていない人だな」と思われてしまいます。
香典袋を渡す際には、ふくさを台にして、その上に香典袋を載せ
相手側に向けて渡すようにしましょう!


慶事・弔事のマナー:香典袋のルール 関連ページ
- 贈答:寸志と松の葉
- 贈答:お中元やお歳暮
- 慶事・弔事のマナー:焼香のやり方を知ろう!
- お客様対応のマナー:お辞儀
- お客様対応のマナー:エレベーター案内のルール
- 身に付けないと損をする!?『仕組み化』思考を習得しよう
- とりあえずコツコツ頑張ってない?KSF思考を身に付けよう!
- 時間密度を高める『ダブルクロッピング思考』とは
- 投資思考でInputを捉え直そう!
- 問題解決はどうやって学べば良いの??
- 神様からのプレゼントは投資資源だった!?時間投資を始めよう!
- 『逆算思考』で始めるプロジェクトマネジメント
- 知ってる人だけやっている手帳活用4つの視点
- 時間があれば出来るのに!?タイムリミットは不要?必要?
- 時間投資の優先度を決定する2×2マトリックス
- 文系でも使える4つの数学的思考テクニック